正社員の勤務時間と法定労働時間は?
正社員の法定労働時間とは
1日8時間、1週間で40時間
従業員の労働時間は労働基準法により定められており、これは正社員でも派遣社員でもバイトでも変わりません。1日8時間、1週間で40時間が法定労働時間として定められています。原則法定労働時間を超えての労働はさせてはいけないと定められています。使用者がこの時間を超えて労働者を働かせる場合、通常賃金の2割5分増しの割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。ちなみに間の休憩時間は法定労働時間には加算されません。
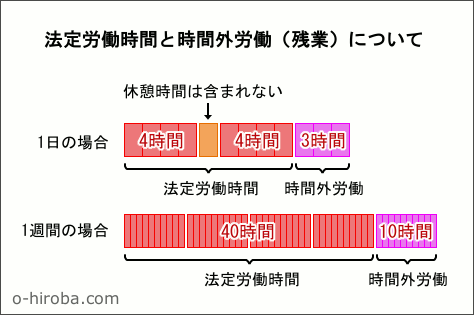
企業によっては上記のような原則では十分に対応しきれない場合もあるので、例外として以下のような制度がいくつか用意されています。
週の法定労働時間が44時間の業種
一部業種では一週間の法定労働時間が44時間に定められているものもあります。商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業等、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店等などが該当し、従業員が10人未満である場合に適用されます。法定労働時間を超えて労働させれる理由
上でも述べた通り労働基準法では法定労働時間を超えた労働や休日出勤をさせてはならないと定めています。にもかかわらず法定労働時間を超えた出勤には残業手当が、休日出勤には休日手当を支給したうえでの労働がなされているのが現状です。ではなぜこのようなことが可能なのでしょうか。
使用者は事前に労働者の過半数が組織する労働組合か、過半数の労働者の代表者と紙面による協定を結び、それを労働基準監督署に届け出することで、協定の範囲内で法定労働時間外での労働や、休日労働をさせることが可能となるからです。これは「労働基準法第36条」を根拠としているので「36協定」とも呼ばれています。
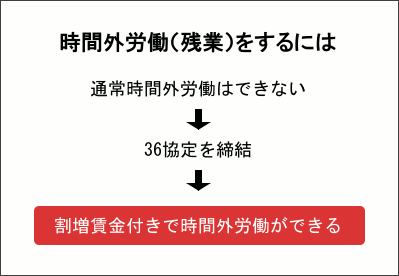
使用者は事前に労働者の過半数が組織する労働組合か、過半数の労働者の代表者と紙面による協定を結び、それを労働基準監督署に届け出することで、協定の範囲内で法定労働時間外での労働や、休日労働をさせることが可能となるからです。これは「労働基準法第36条」を根拠としているので「36協定」とも呼ばれています。
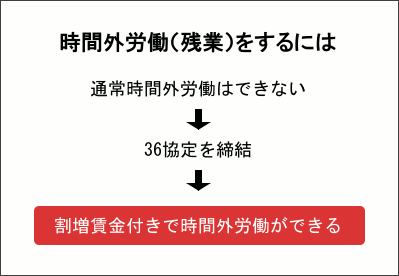
変形労働時間制での勤務時間は?
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは企業が閑散期や繁盛期に応じて、弾力的に労働時間を設定することができるものです。変形労働時間制では1週間、1ヶ月、1年とまずは期間を設定し、その期間内での1週間の平均が40時間を超えない範囲で、定められた限度に応じて労働時間を配分することができる制度です。例えば最初の3週は週5日、1日7時間労働とし、最後の週は週5日10時間労働と設定したとします。この場合変形労働時間制なら、1ヵ月の合算値を1週平均にすると40時間の範囲内に収まっているので、たとえ最後の週が1日8時間を超えていたとしても残業代を支払う必要はありません。
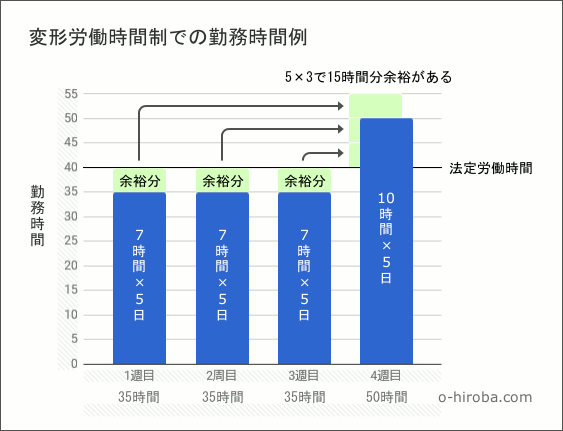
事前に取り決めをしておく必要あり
変形労働時間制を採用するなら、先に就業規則に記載、もしくは労使協定を結んでおく必要があります。その際変形期間と各変形期間の起算日、対象となる労働者の範囲、変形期間中の各日、各週の所定労働時間などもしっかりと定めておかなければなりません。また労働者にも事前に内容を通知しておかなければ有効となりません。
フレックスタイム制での労働時間は?
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは正社員の清算期間(1か月以内)とその総労働時間をあらかじめ決めて起き、その期間内で労働者が自由に始業時間、就業時間を決めれる制度のことです。企業によっては労働者が必ず勤務しておかなければならない時間帯であるコアタイムを設けているところもあります。コアタイムに対して労働者が自由に決めれる時間をフレキシブルタイムといいます。フレックスタイム制では清算期間(1か月以内)の総労働時間を集計し、これを1週平均にして40時間を超えていなければ、たとえ1日8時間、1週40時間を超える日や週があっても残業代を払う必要はありません。
事前に労使協定や就業規則記載が必要
フレックスタイム制を導入するなら事前に労使協定の締結や就業規則への記載などをして、清算期間や清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイムの有無や条件、フレキシブルタイムなどを決めておく必要があります。裁量労働制での労働時間は?
裁量労働制とは業務の性質上使用者の指揮監修にはなじまず、具体的な業務遂行方法については労働者の裁量に任せるものです。具体的に何時間勤務したかは関係なく、勤務時間はその業務を遂行するためにどの程度時間がかかるかをあらかじめ労使協定などで決めておき、その時間を勤務時間とします。
研究開発や弁護士、インテリアーコーディネータなど専門的な職種や、事業運営の企画立案、調査などを行うホワイトカラーなどが対象となります。
研究開発や弁護士、インテリアーコーディネータなど専門的な職種や、事業運営の企画立案、調査などを行うホワイトカラーなどが対象となります。
事業場外労働のみなし制度
営業などで事業場外で勤務する場合、勤務時間の把握が難しいことがあります。このような場合にあらかじめ労使協定などで決めた労働時間を勤務時間とするのが、事業場外労働のみなし制度です。
所定労働時間とは?
所定労働時間とは会社が定める労働時間のことで、法定労働時間の範囲内で決めることができます。所定労働時間を超える勤務は残業として扱われますが、残業代等の支払い義務はありません。あくまで法定労働時間を超えた勤務から残業代の支払い義務は発生します。
会社によっては所定労働時間を超えた勤務にも割増賃金を設定している場合もあります。例えば所定労働時間が7時間の場合、7時間を超える勤務には会社設定の割増賃金が支払われ、法定労働時間の8時間を超える勤務には2割5分増し以上の割増賃金が支払われます。
会社によっては所定労働時間を超えた勤務にも割増賃金を設定している場合もあります。例えば所定労働時間が7時間の場合、7時間を超える勤務には会社設定の割増賃金が支払われ、法定労働時間の8時間を超える勤務には2割5分増し以上の割増賃金が支払われます。
労働時間が週60時間を超えた場合は
週の労働時間が40時間を超えた場合は2割5分増しの残業代を支払う必要がありますが、さらに60時間を超えるとその割増率は5割へと上がります。週40時間というのは5日勤務で1日にすると8時間ですが、これが週60時間にすると1日にして12時間です。毎日12時間勤務というのはかなり過酷な状況です。
そこでこうした企業の長時間労働を抑制するためにも、さらに60時間以上の労働に対して割増賃金の率を高めて企業への負担を大きくしているのです。
そこでこうした企業の長時間労働を抑制するためにも、さらに60時間以上の労働に対して割増賃金の率を高めて企業への負担を大きくしているのです。
勤務時間の集計の単位は
勤務時間は1分単位で集計
正社員の労働時間の集計単位は1分単位が望ましいといえます。企業によっては計算の煩雑さを解消するために10分単位、15分単位、30分単位で集計しているところもあります。この場合問題なのは単位に満たない端数の取扱です。例えば15分単位で集計していて勤務時間の端数が10分だった場合、その10分を切り捨てにすることは労働基準法に反することになります。こうした場合は10分をしっかりと10分として計測するか、もしくは集計単位に合わせて15分に切り上げて計算するかのどちらかを選ばなければなりません。
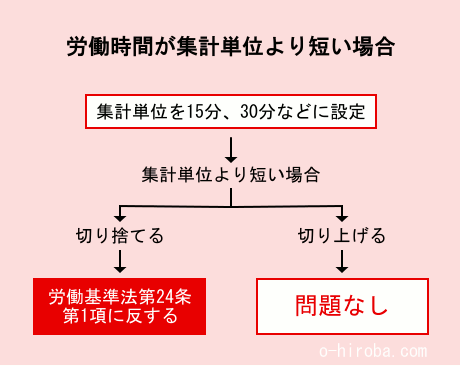
残業時間等なら1か月単位で切り下げも可能
通常の労働時間(法定労働時間)であれば集計単位未満の切り捨ては認められません。しかしながら時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働ではそれぞれの1ヵ月の合計値を集計し、その集計値で端数が生じた場合に、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとすることができます。正社員の勤務時間の集計単位については正社員の時給計算は15分、30分単位?切り捨て・切り上げは労働基準法違反?でも詳しく解説しています。休憩時間について
労働基準法では6時間以上勤務する場合は休憩時間を45分以上、8時間以上勤務する場合は休憩時間を60分以上確保しなければなりません。なお休憩時間は勤務時間には含まれません。
まとめ
法定労働時間を超過する勤務には36協定が必要
労働基準法では1日8時間、週40時間が法定労働時間と定められ、使用者がそれ以上従業員を働かせたい場合は労働組合か労働者の過半を代表するものと36協定と呼ばれるものを労使協定で締結し、就業規則に記載しておく必要があります。そのうえで従業員が法定労働時間を超えて労働した場合は2割5分増しの残業代(割増賃金)を支払う必要があります。変形労働時間制とフレックスタイム制
企業によっては繁盛期と閑散期がはっきりと別れるというところもあります。こうした企業では変形労働時間制とフレックスタイム制を採用しているところもあります。どちらも期間内の総労働時間を集計し、それを週平均にした時に40時間を超えなければ、たとえ1日の労働時間が8時間を超えていても残業代(時間外労働手当)を支払わなくてもいいというものです。ただしこうした制度を利用するためには事前に労使協定を締結し、就業規則に記載しておく必要があります。
| 公開日 2018/06/10 |
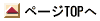
|
 
|
| 就職・転職 |
 |
|
since 2003/03/11 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved | |




